「寒中見舞いをもらったけど、どう返したらいいんだろう?」そんなふうに戸惑ったことはありませんか?年賀状の時期が過ぎたころに届く寒中見舞いは、季節のあいさつや相手を気遣う気持ちが込められた大切な便りです。
けれども、喪中や年賀状のやりとりとの関係が少し複雑なため、「返事を出すべき?」「いつまでに出すの?」と悩む人が多いものです。
この記事では、寒中見舞いをもらったときの基本マナーから、返事の判断基準、相手別の文例までをわかりやすく解説します。
初めての方でも安心して対応できるよう、やさしい言葉で丁寧にまとめました。この記事を読み終えるころには、心のこもった一通を自信を持って送れるようになりますよ。
寒中見舞いをもらったときの基本マナー
そもそも寒中見舞いとは?意味と時期
寒中見舞いとは、一年で最も寒い時期に相手の健康を気づかうための挨拶状です。年賀状の時期(1月7日頃)を過ぎてから、立春(2月4日頃)までの間に送るのが一般的なマナーとされています。
つまり、「お正月の挨拶ができなかった人」や「喪中の相手に対して季節の挨拶をしたい人」が使う、やさしさのこもった便りなのです。
この時期に送られるため、寒中見舞いは年賀状とは目的が異なります。年賀状が「新年の喜びを伝えるもの」であるのに対し、寒中見舞いは「寒さをいたわる気持ちを伝えるもの」。
そのため、華やかな賀詞やおめでたい言葉は避けるのが基本です。
寒中見舞いをもらうシーンは?(喪中・年賀状の代わりなど)
寒中見舞いが届く背景には、いくつかのパターンがあります。
- 相手が喪中の場合:年賀状の代わりに「ご挨拶が遅れました」と寒中見舞いを送るケース。
- 自分が喪中だった場合:相手が気遣いを込めて送ってくれるケース。
- 年賀状の返礼やお詫び:年賀状を出せなかったり、遅れてしまったときのフォローとして出されることも。
つまり「寒中見舞いをもらった」ということは、相手がこちらを思って丁寧に挨拶してくれたサインです。まずはその気持ちに対して「ありがたいな」と思うことが第一歩です。
もらった側がまず意識すべき3つのポイント
寒中見舞いを受け取ったときは、次の3つを意識しておくと安心です。
- 受け取った日付を確認する
返事を出すなら、なるべく早め(1週間以内が理想)に対応するのがマナーです。 - 相手の状況を読み取る
喪中なのか、年賀状の代わりなのかによって返事の内容が変わります。 - 自分の状況に合わせて判断する
自分が喪中なら「返事は出していいのか?」と悩むことも。後ほど詳しく説明しますが、喪中でも寒中見舞いとしての返信は問題ありません。
寒中見舞いは「気持ちのやり取り」です。形式ばかりを気にするよりも、相手を思いやる心を忘れないことが何より大切です。あなたもまずは、「送ってくれてありがとう」という気持ちを込めて受け取りましょう。
返事は出す?出さない?判断の基準を整理
返信が必要なケース/不要なケース
寒中見舞いの返事は、必ず出さなければならないわけではありません。しかし、相手との関係性や状況によって対応は変わります。以下のように整理するとわかりやすいでしょう。
| 状況 | 返信の必要性 | 対応のポイント |
|---|---|---|
| 相手が喪中で、年賀状の代わりに寒中見舞いを送ってきた | 出すのが望ましい | 「お心遣いありがとうございます」「寒い日が続きますがお身体を大切に」など、丁寧なお礼を添える |
| 自分が喪中で、相手から寒中見舞いをもらった | 出してもOK | 「ご丁寧なお見舞いをありがとうございます」と返すと印象が良い |
| 年賀状を出せなかった相手から届いた | 出すのがおすすめ | 「年始のご挨拶が遅れました」と添えて寒中見舞いとして返す |
| ビジネス相手から届いた | 出すのがマナー | 感謝と今後のご縁を意識した文面を選ぶ |
| 親しい友人・知人から届いた | 状況に応じて | 口頭やメッセージでお礼を伝えるだけでもOK |
基本的には「お世話になっている相手」や「心のこもった便りをもらったとき」は、返信するのが丁寧です。形式的な義務ではなく、「気持ちを返す」というスタンスが大切ですね。
出す場合のタイミングと期限
寒中見舞いの返信は、立春(2月4日頃)までに届くように出すのがマナーです。もらってから1週間以内に準備を始めると、余裕を持って対応できます。
もし間に合わなそうな場合は、立春を過ぎてから「余寒見舞い」として出すのもOK。「寒さが残る折、いかがお過ごしでしょうか」といった表現に変えるだけで、自然に季節の流れを感じさせる挨拶になります。
ポイントは「届いたらすぐ対応すること」。早めの返信ほど、相手への感謝が伝わります。
返事を出さないときの丁寧な対応例
寒中見舞いをもらっても、状況によっては返信を控えたほうがよい場合もあります。
たとえば
- 相手が喪中で、こちらも特に近しい関係でない場合
- メッセージや口頭で既に感謝を伝えている場合
- SNSやLINEなど、カジュアルなやり取りで済む関係性のとき
そんなときは、無理にハガキを出す必要はありません。代わりに、次に会ったときやメッセージで「寒中見舞いをありがとう」と一言伝えるだけでも十分です。
大切なのは「形式よりも気持ち」で、無理なく、自分らしい形でお礼を伝えることが、最も心に残る対応です。
寒中見舞いの返信マナーと書き方
返信文に盛り込むべき内容
寒中見舞いの返信では、次の4つの要素を押さえておくと、自然で礼儀正しい文章になります。
- 季節の挨拶(寒中お見舞い申し上げます など)
まずは定番の挨拶文から始めて、相手の体調や健康を気づかう一言を添えます。 - 相手の寒中見舞いへのお礼
「ご丁寧なお見舞いをありがとうございました」など、感謝の気持ちを明確に伝えましょう。 - 自分の近況や相手への思いやり
「私どももおかげさまで元気に過ごしております」など、短く自分の状況を伝えると印象が柔らかくなります。 - 結びの言葉(相手の健康や幸せを祈る)
「まだ寒さが続きますので、どうぞご自愛ください」といった締めくくりが基本です。
文章の長さは、はがき1枚におさまる程度で十分。形式よりも、「あなたの気持ちが伝わるか」を意識するのがコツです。
文面の基本構成と注意点
寒中見舞いの返信文は、以下のような流れを意識すると美しくまとまります。
① 季節の挨拶
② お礼の言葉
③ 自分の近況報告
④ 相手への気づかいと結び
例えばこんな形です👇
〈返信文の例〉
寒中お見舞い申し上げます。
ご丁寧なお便りをいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで私どもも変わりなく過ごしております。
寒さ厳しい折、どうぞお身体にお気をつけてお過ごしください。
短くても、この構成を守るだけで丁寧で温かい印象になります。また、文章は「です・ます調」で統一し、句読点を打ちすぎないのが和文マナーとして自然です。
避けたい表現・失礼にならないコツ
寒中見舞いは、「お祝い」ではなく「お見舞い」の文書です。そのため、以下のような表現は避けるようにしましょう。
| NGワード | 理由 |
|---|---|
| あけましておめでとうございます | 新年を祝う言葉のため不適切 |
| 賀正/寿/迎春 など | 年賀状用の賀詞なので使わない |
| お幸せをお祈りします | 喪中の相手には避けるのが無難 |
| 早く元気になってください | 病気ではない場合に誤解を招くことも |
また、差出人欄の「住所・氏名」は丁寧に書くこと。返事を出す相手がビジネス関係なら、会社名や肩書きを添えるとより印象が良くなります。
ちょっとした心づかいが、相手の心に温かく残る寒中見舞いになります。マナーを押さえたうえで、自分らしい言葉を添えるのが一番大切ですね。
相手別の返信文例集(友人・ビジネス・喪中など)
親しい友人への返信文例
親しい間柄では、形式ばかりにとらわれず、やわらかい言葉で気持ちを伝えるのがおすすめです。少しカジュアルでも、「季節の挨拶+感謝+近況+気づかい」の流れを守ればOKです。
寒中お見舞い申し上げます。
お便りをありがとう。お互い元気に過ごしているようで何よりです。
今年も寒さが厳しいですね。体調に気をつけて、また落ち着いたら会いましょう。
💡ポイント:親しい相手には、「ありがとう」や「また会いたいね」など、あたたかい言葉を添えると印象がやわらぎます。
上司・取引先など目上の人への返信文例
ビジネス関係の相手には、簡潔で礼儀正しい文体を心がけましょう。形式的でも、誠実な印象を与えることが大切です。
寒中お見舞い申し上げます。
ご丁寧なお見舞い状をいただき、誠にありがとうございました。
おかげさまで私どもも変わりなく業務に励んでおります。
寒さ厳しき折、皆様のご健康とご発展をお祈り申し上げます。
💡ポイント:会社名や役職を入れる、句読点を控えめにするなど、ビジネスマナーを意識しましょう。
喪中の相手に出すときの文例
喪中の相手には、「おめでたい言葉」を避けつつ、静かに思いやりを伝えます。あくまでお見舞いの気持ちを中心にするのがコツです。
寒中お見舞い申し上げます。
ご丁寧なお便りをいただき、誠にありがとうございます。
ご家族の皆様もお疲れのことと拝察いたします。
どうぞご無理なさらず、お身体を大切にお過ごしください。
💡ポイント:「ご冥福」や「お悔やみ申し上げます」は、既に忌明け後であれば避けたほうが自然です。
メールやLINEで返信するときの注意点
最近では、寒中見舞いの代わりにメールやLINEで挨拶を交わす人も増えています。ただし、ビジネス関係や年配の方にはハガキの方が印象が良いことを覚えておきましょう。もしカジュアルな関係でメッセージを送るなら、こんな形がおすすめです👇
寒中お見舞い申し上げます。
メッセージありがとう!寒い日が続くけど元気にしてます。
○○さんも体調に気をつけて、あたたかく過ごしてくださいね。
💡ポイント:スタンプや絵文字を使う場合は控えめにし、相手との関係に合わせてトーンを調整しましょう。
相手や状況によって言葉を少し変えるだけで、受け取る印象はぐっと変わります。大切なのは「形式よりも思いやり」。あなたらしい温かい一文を添えることで、心が伝わる寒中見舞いになります。
返信が遅れたとき・出しそびれたときの対応
期限を過ぎた場合の対応マナー
寒中見舞いは通常、立春(2月4日ごろ)までに届くように出すのがマナーです。
もしその時期を過ぎてしまった場合は、「余寒見舞い(よかんみまい)」として出せば大丈夫です。余寒見舞いは、立春後〜2月下旬ごろまでに出す季節の挨拶で、「まだ寒さが残る折にお伺いします」という意味を持ちます。
余寒お見舞い申し上げます。
ご丁寧なお便りをありがとうございました。
暦の上では春とはいえ、まだ寒さが続きますね。
どうぞお身体にお気をつけてお過ごしください。
💡ポイント:「寒中お見舞い」ではなく「余寒お見舞い」に言い換えるだけで、自然で時期に合った印象になります。
「余寒見舞い」として出すタイミング
余寒見舞いを出すベストタイミングは、立春の翌日〜2月20日頃まで。地域によってはもう少し寒さが続くので、2月末までならマナー違反にはなりません。3月以降になると、季節の挨拶としてはやや遅い印象になるため、その場合は「春のご挨拶」など別の表現に切り替えましょう。
遅れても気持ちが伝わるフォロー方法
「すっかり時期を逃してしまった…」という場合でも、心を込めてフォローすれば失礼にはなりません。たとえば次のような形で、遅れたことを軽くお詫びしながらお礼を伝えると好印象です。
ご挨拶が遅くなり申し訳ございません。
先日はご丁寧なお見舞いをいただき、ありがとうございました。
遅ればせながら心より感謝申し上げます。
また、親しい相手ならメールやLINEで「寒中見舞いありがとう、返信が遅れてごめんね!」と伝えるだけでも十分。大切なのは、「忘れていた」ではなく「きちんと受け取って、感謝している」という気持ちを形にすることです。
少し遅れても、心を込めて言葉を贈ることができれば、それは立派なマナーです。人と人とのつながりは、完璧さよりも温かさが伝わるかどうか。遅れを恐れず、素直な言葉で思いを伝えましょう。
寒中見舞いをもらったときのよくある疑問まとめ
年賀状を出していない相手から来たらどうする?
年賀状を出していない相手から寒中見舞いが届いた場合は、お礼を込めて寒中見舞いで返すのが丁寧です。
「ご丁寧なお便りをありがとうございました。寒さ厳しい折、どうぞご自愛ください」などの短い一文でも構いません。「年賀状を出せず失礼しました」と添えると、気持ちのこもった印象になります。
喪中の相手から寒中見舞いをもらった場合は?
喪中の方から寒中見舞いが届いた場合、こちらからも寒中見舞いで返信して問題ありません。
ただし、「お悔やみ」や「ご冥福」などの表現は避け、「寒さ厳しき折、ご自愛ください」など、相手を気づかう言葉を中心にしましょう。哀しみに寄り添う静かな優しさが伝われば十分です。
寒中見舞いがメールやSNSで届いた場合も返信する?
メールやLINEで寒中見舞いをもらった場合も、できれば返信するのがマナーです。
形式にこだわる必要はありませんが、「お心遣いありがとうございます」「○○さんもお元気で過ごしてくださいね」といった一文を返すと好印象です。ビジネス関係の場合は、簡潔なメール文面でもOKです。
ビジネス相手に返事を出すときの封筒やはがきの選び方は?
ビジネスシーンでは、白無地または淡い色のはがきが最も無難です。
イラスト入りや華やかなデザインは避け、清潔感・誠実さを重視しましょう。封書で出す場合は、便箋も無地が基本。筆ペンや黒インクのボールペンで丁寧に書くと好印象です。
寒中見舞いをもらったけど返せない関係性のときは?
たとえば疎遠になってしまった人や、ビジネス上もう関わりのない相手など。無理に返事を出さなくても問題はありません。
ただ、次に何かの機会で連絡を取る際に「寒中見舞いありがとうございました」と一言添えると、印象がぐっと柔らかくなります。「無視」ではなく「心で受け取る」姿勢が大切です。
寒中見舞いは、形式的な手紙ではなく「相手を想う気持ち」を伝えるもの。小さなやり取りの中に、優しさや思いやりがにじむ季節の風物詩です。あなたもぜひ、相手の心をあたためる一通を送ってみてくださいね。
まとめ
寒中見舞いをもらったときの対応は、難しそうに見えて実はとてもシンプルです。
大切なのは「相手の気持ちを受け取り、思いやりを返すこと」。
返信の要不要や文面の細かいマナーよりも、感謝の気持ちを丁寧に伝える姿勢が一番のポイントです。
寒中見舞いは、年賀状の時期を過ぎても人と人とのつながりを感じられる、温かい日本の習慣。
少しの気づかいで、相手の心に残る一通を届けることができます。
私自身も、寒中見舞いをきっかけに久しぶりの友人と再び連絡を取れたことがあります。
「手紙っていいな」と改めて感じた瞬間でした。
この記事が、あなたの気持ちを伝えるお手伝いになれば嬉しいです。
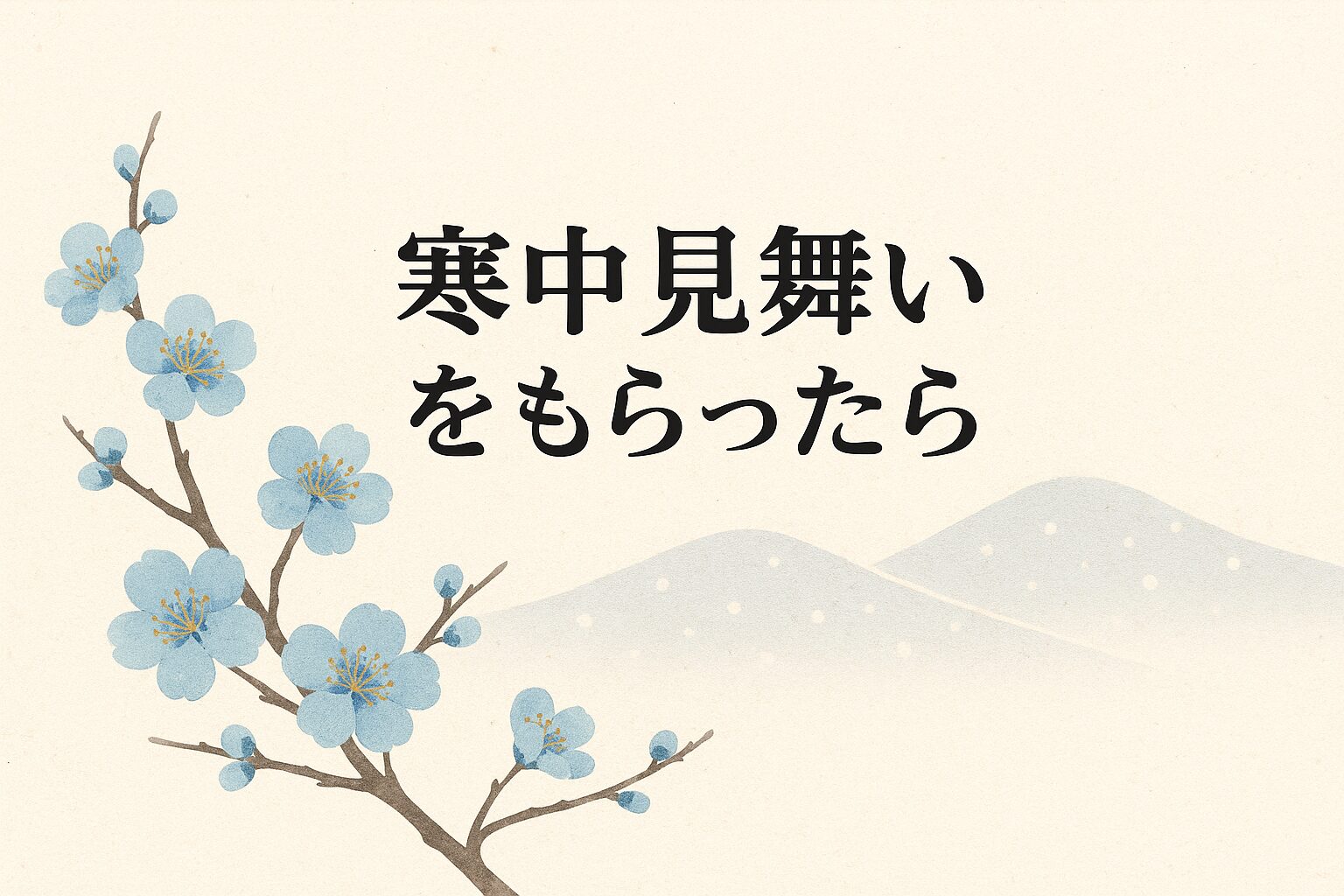


コメント