「おもたせ」という言葉を耳にしたことはあっても、正しい意味や使い方をすぐに答えられる人は意外と少ないのではないでしょうか。
手土産との違いや、どんな場面で使うのが適切かを知っておくと、日常会話やビジネスシーンでも役立ちます。
この記事では、「おもたせ」の意味や使い方、よくある誤解や表現例をわかりやすく解説します。
おもたせとは?基本の意味をわかりやすく解説
「おもたせ」という言葉は、日常生活の中でお菓子や手土産に関連して耳にすることが多いでしょう。しかし、その正しい意味や使い方を知っている人は意外と少ないかもしれません。
ここでは、「おもたせ」の基本的な意味や成り立ちをやさしく解説していきます。
「おもたせ」の語源と成り立ち
「おもたせ」とは、来客が持参した手土産のことを、受け取った側がへりくだって呼ぶ言葉です。
語源は「持たせる」という動詞に丁寧語の「お」を付けたもの。
つまり「お持たせ」が原型であり、謙譲表現として相手に敬意を示す言葉になっています。
手土産との違いは?
「手土産」と「おもたせ」は似ていますが、使う立場が違います。
- 手土産 … 持っていく側が使う言葉
- おもたせ … 受け取った側がへりくだって使う言葉
例えば、訪問先にお菓子を持っていくときは「手土産」と言いますが、受け取った側がお菓子をお茶と一緒に出すときに「おもたせですが」と表現します。
日常で使うときのニュアンス
「おもたせ」という言葉には、日本的な気遣いや謙遜の文化が込められています。
例えば、来客にお菓子を出すときに「おもたせですが、どうぞ」と伝えることで、「いただいたものをお出しする形になりますが…」という控えめな気持ちを表現できます。
一方で、使い方を間違えると「他人からもらったものをそのまま出している」と強調してしまい、少し失礼な印象になる場合もあります。
文脈や関係性を考えて使うのが大切です。
おもたせの正しい使い方とマナー
「おもたせ」という言葉は、日本の謙譲表現のひとつです。
ただし、日常会話やビジネスシーンで使うときには注意が必要です。ここでは、正しい使い方とマナーについて詳しく見ていきましょう。
おもたせを使う場面
「おもたせ」という表現は、主に来客からいただいた品を食事やお茶と一緒に振る舞うときに使われます。
たとえば、友人が遊びに来た際にいただいたお菓子をお茶うけに出すときに「おもたせですが、どうぞ」と伝えるのが自然です。
また、改まった食事会や法事などでも使われることがあり、場の雰囲気を和らげる役割も果たします。
失礼にならない言い回し
「おもたせ」という言葉自体には謙遜の気持ちが込められていますが、場合によっては「いただきものをそのまま出している」というニュアンスが強調されてしまうこともあります。
そのため、以下のような言い回しに工夫すると好印象になります。
- 「おもたせですが、どうぞ召し上がってください」
- 「先ほどいただいたお菓子を一緒にいただきましょう」
- 「おもたせいただいたもの、とても美味しそうなのでお茶と一緒に」
「おもたせ」という言葉を強調しすぎず、場を和ませる表現にするのがポイントです。
ビジネスシーンでの注意点
ビジネスの場面では、「おもたせ」という表現は慎重に使う必要があります。
特に、取引先や上司に対して「おもたせですが」と言うと、「自分で用意したものではないのか」と誤解を招く恐れがあります。
そのため、ビジネスでは次のような言い換えが好まれる場合があります。
- 「本日は素敵なお品をいただきありがとうございます」
- 「いただいたお菓子を皆さまでどうぞ」
つまり、日常会話では気軽に使える一方で、フォーマルなシーンでは控えめに、または別の表現を選んだ方が安心です。
よくある誤解と間違いやすいポイント
「おもたせ」という言葉は上品で便利な一方で、誤解や誤用が多い言葉でもあります。ここでは、特に間違えやすいポイントを整理して解説します。
「おもたせ=手土産」ではない?
もっとも多い誤解は、「おもたせ=手土産」と考えてしまうことです。
実際には、手土産は持参する側の言葉、おもたせは受け取った側の言葉であり、使う立場が逆になります。
例えば、訪問する側が「おもたせを持ってきました」と言うのは誤用です。この場合は「ささやかですが手土産を持参しました」と言うのが正解です。
「いただきもの」との違い
「おもたせ」と「いただきもの」も似ていますが、意味が異なります。
- いただきもの … 単に「人からもらったもの」というニュートラルな表現
- おもたせ … いただいたものを相手に出すときの、へりくだった言い方
例えば「先ほどいただいた和菓子です」と言えば十分ですが、「おもたせですが」と言うと、謙遜のニュアンスが加わります。どちらを選ぶかは場の雰囲気や相手との関係性によります。
使い方を間違えたときの印象
「おもたせ」を誤用してしまうと、相手に不自然な印象を与えることがあります。
特に気をつけたいのは次のようなケースです。
- 持参する側が「おもたせですが」と言ってしまう → 自分でへりくだるのは不自然
- 会社訪問で「おもたせのお菓子です」と渡す → 言葉の使い方として誤り
- いただきものをそのまま出したことを強調してしまう → 気配りに欠ける印象
つまり、「おもたせ」は便利な表現ですが、場面や立場を間違えないことが大切です。
おもたせを使った表現例
「おもたせ」という言葉は、実際の会話や場面でどう使うのかが一番気になるところですよね。ここでは、来客や食事会などで自然に使える例文をシーン別に紹介します。
来客時のお菓子を出すときの一言
友人や知人が訪ねてきた際に、持参してくれたお菓子をお茶と一緒に出す場面でよく使われます。
- 「おもたせですが、ご一緒にどうぞ」
- 「ちょうどいただいたお菓子がありますので、ぜひ召し上がってください」
このように控えめに伝えることで、相手に喜んでもらいながらも謙遜の気持ちを表現できます。
食事会での自然な言い回し
ホームパーティーや親戚の集まりなどでは、料理やお菓子を出す際に「おもたせ」を使うと場が和みます。
- 「おもたせいただいたワインで乾杯しましょう」
- 「皆さまでおもたせの和菓子をいただきましょう」
特に食事会では、提供する側が自分の手柄ではなく相手のおかげと表現することで、謙虚さを感じさせられます。
英語で表現するなら?
「おもたせ」に完全に一致する英語表現はありませんが、状況に応じて言い換えられます。
- 「This is a gift from our guest. Please enjoy it.」
- 「We were given this sweet, so let’s have it together.」
日本語の「おもたせ」が持つ謙遜のニュアンスをそのまま英語にするのは難しいため、シンプルに「guest brought」や「gift」を使って伝えるのが自然です。
日本文化における「おもたせ」の位置づけ
「おもたせ」という言葉は、単なる手土産の呼び方以上に、日本人の価値観や人間関係のあり方を映し出す言葉です。ここでは、日本文化との結びつきや現代における意味合いについて考えてみましょう。
贈答文化とのつながり
日本には昔から、贈り物を通じて感謝や敬意を伝える「贈答文化」が根付いています。お中元やお歳暮といった季節の贈り物もその一例です。
「おもたせ」は、そうした贈答の一部である“手土産”をさらに受け取った側がへりくだって表現する言葉であり、贈り物に対する感謝の心を示す役割を担っています。
謙遜と気遣いの表現
「おもたせ」という言葉には、相手を立てて自分を控えめにする日本的な謙遜の精神が込められています。
- 自分のもてなしを誇張せず、相手からいただいたものを中心に場を和ませる
- 「もらったものをそのまま出す」ことをあえて言葉にすることで、率直さや誠実さを表現する
このように「おもたせ」は単なる言葉以上に、日本人特有の気遣いのあり方を象徴しています。
現代における「おもたせ」の使われ方
近年ではライフスタイルの変化もあり、「おもたせ」という言葉は少し古風でフォーマルな印象を持たれることもあります。しかし、冠婚葬祭や格式ある場面では依然として使われることが多く、大人の語彙として知っておくと役立ちます。
また、カジュアルな場面でも「おもたせですが」と一言添えるだけで、場が和み、相手への敬意や感謝を自然に表すことができます。
現代においても、「おもたせ」はコミュニケーションを円滑にするための便利な表現なのです。
まとめ
「おもたせ」という言葉は、単に「手土産」と同じ意味ではなく、いただいた品を受け取った側がへりくだって表現する日本独特の言葉です。
- 手土産=持っていく側の言葉
- おもたせ=受け取った側の言葉
この違いを正しく理解することが、自然で失礼のない使い方につながります。
また、ビジネスシーンでは誤解を招かないよう注意が必要ですが、家庭や友人とのやり取りでは「おもたせですが、どうぞ」と使うことで、場を和ませつつ謙虚な気持ちを伝えることができます。
現代では少し古風な響きがあるものの、大人の教養として知っておくと安心できる表現です。
日本文化の中で育まれてきた謙遜や気遣いを体現する言葉として、「おもたせ」を上手に使いこなしていきましょう。


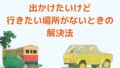
コメント